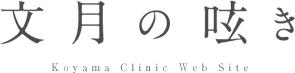時世の粧い
百歳時代と聞いて
2018年06月10日
テレビを見ていたら、百歳まで生きる時代、と保険会社のCMで言っていた。果たしてそんな時代なのか、診療していてまだ実感がない。そういえば今年は、先だって十三回忌を済ませた父の生誕100年にあたる。その父が7歳の誕生を迎えた日は、父の母親が亡くなった日でもある。祖母享年29歳、今から93年前のことである。
私の家の仏間には、その祖母がグランドピアノに譜面を置いて弾いている一枚の写真がある。母によると、ピアノは私の祖父が東京の三越で買ったものだそうだ。当時、祖母がどのようにしてピアノと関わっていたのだろうか。父は生前ほろ酔い機嫌でピアノを弾いていた。私が小さい頃、2歳下の妹と一緒に父の弾くピアノに合わせて歌ったものだ。晩年もよく弾いていて、もう私は歌わないにしても、時々は脇で見ることがあった。父のピアノは、右手のメロディに合わせて伴奏する左手が、右手の動きに連動して両手の間隔は変わらない弾き方なのである。しかも、少なくとも鍵盤を上から叩いていた。これは、病弱だっただろう祖母から教えてもらった形跡ではないかと想像した。
さて、井上靖の「わが母の記」の中に、「父が亡くなってから、私は何でもないふとした瞬間、自分の中に父がいることを感じるようになった。」と書かれている。さらに、「父という一人の人間のことを考えることが多くなった」とも書かれていて、私も正に父を想うこの頃である。実は今年は、私が父と一緒に開業を始めた時の父の年齢に到達した年でもある。開業当初は、父のような高齢の医者と一緒に仕事したことがなく、これまでにない診療を目の当たりにした。最近になって、私の仕草や格好、つまり小児を診たり、大人の生活習慣について患者さんに話したりしている自分が、妙に父に似ていると思うのである。若さ故か、当時はどちらかというと否定した父の診療の姿を、いま踏襲している。輪廻というと大げさか。しかし、遺伝子でつながれた親子はこうして世の中を紡いでいくのかと思う。
私は音楽に熱中し、殊にピアノ好きになった。妹はピアノ科に進んだ。これも三越から運ばれたピアノに端を発して、遺伝子ではない音楽魂のようなものが引き継がれたのではないかと愚考していたら、ある日、母がピアノの前に座って、急に弾きだしたではないか。聞いたら、子どもの頃に家にあったオルガンを我流で弾いて曲を覚えたそうだ。今の今まで、母とピアノとは結びつかなかった。引き継ぐ音楽魂については、考え直してみることとする。
そろそろ今年も父の日が巡ってくる。以下は、父が亡くなった年に記したものである。
<ワイシャツの襟>2006/08
大阪に行ったときのことである。普段はラフな格好でいることが多いのに、その日は、ワイシャツにネクタイを締めて一日中行動した。家に帰ってきてから、ワイシャツの襟が黒く汚れていないことに気づいた。昔東京で生活していた頃は、一日着ると真っ黒になってしまったのに、幾星霜を経て新陳代謝が落ちてしまったと思った。そういえば、昔から父が脱いだワイシャツを見ても、あまり汚れがなかったということを思い出した。
早いもので、私が父と一緒に開業してから、今年の春でちょうど20年になった。そして、そのような節目の今年、父が他界した。親の思い出は、それぞれがさまざまにあるように、私にもいくつもある。
昔、父がスクーターに乗って往診していた姿を見かけた方が、姿勢が良いですね、と言ってくれた。このようなことを言ってくれた背景には、父のまじめさがあったからだ、と思っている。実は、父の腰椎は癒合していて、姿勢が良くならざるを得なかったのだが。
父は、診療中多くの医者と同じように、白衣をまとっていた。しかし、白衣を着ないで仕事している私をみて、いつの間にか、父も白衣を脱いで、私服で仕事をするようになった。晩年は、診察室に来られた同年代の患者さんと、南方の地図を広げて、診察そっちのけで戦争談義に花を咲かせていた。私と仕事をすることで、まじめだった父の中で、何かが崩れていったのかも知れない。
その父を自宅で看取った。自宅での治療は、病院のようなわけには行かず、検査値を始めとした客観的なデータが乏しかった。治療のための手がかりがもう少し欲しい、という気持ちで、私は、父の眼と表情を見た。最期が近づいているにもかかわらず、表情は良かった。そして、医師である父の方は、お前に任せたともとれるような眼で、私をみていた。言わば父の物言わぬ思いを私が代行した、といったら良いだろうか、表情が良いから輸液量を加減する、というように治療を進めた。それは、あまり科学的ではなく、良い治療だったかどうかは、今もってわからない。そのようなやりとりを重ねているうち、父は逝った。
私の記憶にある父は、もうすでに年を取っていたのだろう。その当時は、ワイシャツの汚れが少ない、などと父を思いやる自分ではなかった。自分が同じような年になって、やっと気づいたときには、もう父はいなかった。今、家の中にある父のワイシャツは、白いまま整然と納まっている。
母の手術
2018年05月23日
このところ、93歳の母のことで時間が割かれた。先日は、請われて横浜に旅をする手伝いをした。2泊3日と余裕を持たせたのに、都合で日を短縮したため、あわただしいクルマでの往復となった。短時日での往復1000キロ運転は、クルマ好きの私でも、さすがにこたえた。高齢の母もかねてより行きたかったという気持ちが勝ったものの、疲れた様子が在り在りであった。
その次は、右手の手術。昨年秋頃より右親指と人差指の自由が利かなくなり、整形外科で手根管症候群とばね指と診断された。どうも、台所でカボチャを切るなど、がんばり過ぎて腱鞘炎を起こしたらしい。こちらは旅のあと手術を受けた。無事に終わって、二本の指の動きが元に戻りつつある。
当日、手術室から病室に戻ったとき、この何か月もの間、動きの悪かった指をわずかながら動かすことが出来たことに驚いていた。これで死ぬまで普通の指でがんばることが出来る、あるいは、死ぬときに普通の指でいられる、というようなことを言っていた。最期まで普通の指でいられることを望むのは、母らしい性格から出た言葉か。母は、うまくいった手術に気分が高揚したのか、色んなことをしゃべった。先に記したことのほか、執刀医への感謝の言葉、まだまだ活動できそうだという前向きなことなどである。いくつかの感情が交錯したなかで、おそらく、指が術後思ったより早く動いたことから、実利を越えて、より良い指をひとに見せたいという気持ちでいるのだろう。
世間では、こうして私が携わったことを親孝行と呼ぶのだろう。しかし、横浜に旅をして母も疲れが癒えぬ手術前の数日、90歳を超えた身で受けることを逡巡していたことに、何の医学的アドバイスも出来なかった。医者の立場での親孝行が出来なかった悔悟の念あり。結果的に、母の英断に依ったからだ。
これからは、カボチャを切ることはやめてもらって、精々ネギを切るくらいの手仕事で済ませるよう願っている。私はというと、後回しにした幾つかの楽しみ事に勤しんでいる。
人はみな草のごとく
2018年05月13日
スタインベックの長編、「怒りの葡萄」を読み終えたのは、2年前の2016年だった。それまで、自分の置かれた環境のあわただしさを理由にして、長編ものを敬遠していたのに、これが契機になって、その後は「鹿の王」を読み、長めの映画もいくつか観るようになった。短編ものとは違う時間の流れを感じる。「エデンの東」を観たのはいつだっただろうか。これは、愛車ポルシェで事故を起こして若死にしたジェームス・ディーンの容貌から、甘い恋愛ものであることを想像したが、親子関係の問題から始まり、父の愛を知るようになるまでの映画であった。どちらかと言うと重たい内容で、原作がスタインベックと知って納得した。読書、映画鑑賞を余暇の日課の如く過ごしているこの頃である。
昼過ぎに仕事を終えた日曜の午後、「ドクトル・ジバゴ」を観た。これは20世紀初頭にロシアで革命の嵐が吹き荒れた時代のドラマである。タイトルにあるように、医者が主人公。早くに親を亡くして、医学者に引き取られてから医者となったものの、激しくなった内戦に巻き込まれる。反革命分子の烙印を押されたり、スパイと間違えられたりし、しかも飢えて物資が不足している極寒の地での診療を余儀なくされるなど、劇的な場面が次から次へとあらわれる。そんな中で、妻以外の女性と関係を持ち、二人の間に出来た娘が映画の冒頭と終わりに出てきて、3時間半に及ぶ映画の輪郭を作っている。
ドラマとは言え、戦争という極限状況で診療をしなければならない主人公の心境に思いが至る。自分の死と隣り合った状況での診療とは、どのようなものか。長いドラマの中で、医者の立場から何度も問いかけたくなった。先の大戦で私の父は、オーストラリアの近くのチモール島に軍医として赴任した。父の世代や現在の国境なき医師団は、戦火での診療を経験しているのだ。生前、父は戦地に赴いたことをよく話していたが、過酷な状況での苦労話は一切しなかった。戦友とともに記録に残したものを読んでも、叙事文であるので、心境を垣間見ることはできない。それでも、船が沈没して九死に一生を得たことは聞いたことがあり、小説より奇な運命に遭遇したことは確かである。
以前に読んだ精神科医の中井久夫さんの書物に、トイレを済ませないときちんとした診療が出来ないというようなことが書かれていた。仕事するには、体調を十分にしておくことが要るのは、私も経験上わかることである。それにしても、私を始めとして多くの医者は、平和な時代に診療をするのである。戦地でのように、体調十分も何もなく、否が応でも診療を始めなければならないことは、やはり想像など出来ないことである。それがドラマを観終わっての感想である。
夜になってEテレで放映していたブラームスのドイツレクイエム(死者のためのミサ曲)を聴いた。第2曲では、人はみな草のごとく、草は枯れて、というペテロの第一の手紙が歌詞として歌われる。父も国境なき医師団も、草のように自分を思ったことがあるのだろうかと、ふと連想した。私も立場こそ違え、傍観者ではない。
親バカ
2018年02月25日
先日、娘婿が行なった仕事の内容がよかったのか、全国紙に取り上げられたことを知った。私の日常にはないことであり、掲載している何紙もの新聞記事をネットで検索して保存した。この私の行ないは、親バカならぬ舅バカだと思っていたある日のこと、知人から自身の子どものことについて相談された。知人は、自分は親バカであるから、何とかならないものかと悩んでいるのだとのこと。
悩みに答えながら、親バカの言葉に違和感を抱いた。それは、親であれば子どものことを心配するものであるし、自分で解決できなければ、誰かに相談するということは、当たり前のことである。知人はバカではないのに、バカだと言ったことに違和感があったのだ。この言葉を正しく知りたくて、広辞苑を引いた。親馬鹿とは、子どもへの愛情に溺れて、はた目には愚かに見えるのに、自分は気がつかない、と書かれている。つまり、知人は自分を揶揄して使っているだけで、バカではないと思うのだ。では、私もバカではないのだろうかと改めて考えた。そう、私はただうれしくて、娘婿の業務を書いた記事をとっておきたかっただけである。どうも、私も愛情に溺れているわけではなく、バカではなさそうだ。
さて、手元には1955年に発行された広辞苑の初版本があり、そこにも親馬鹿のことが書かれている。おそらく戦後も使われていたのだろう。ところが、明治期に編纂された日本初の国語辞典である玄海には、この言葉はない。「親思う心に勝る親心」はあったが、親馬鹿は、現代が作った意味、内容か。私や知人のように、気軽に使うのは、高々数十年のことだろうか。これは、親子の在りようが変化して、現代は子どもに過度に愛情をそそぐようになったからではないか、と想像した。
私は自分がバカだと思いながら、この言葉が浮かんだ。しかし、辞書にあるように、自分で気がつかない、ということが要点で、気軽に使うには、もっとバカさ加減が要ると思った次第である。
書評を通して
2017年05月14日
新聞や雑誌に掲載されている書評は、本を購入する参考にするから重宝にしている。しかし、書評のなかの何を理由に本を選ぶのかということを、はっきりと自覚せぬまま、今に至った。書かれた文章に好き嫌いの感情があり、そんなことが本選びにどう影響したのか考えてみた。
私が学生だった頃、同い年の旧友と読書の話をしていた時だったと記憶しているが、ある人物が各新聞を読み漁った結果、朝日の書評が一番いいと言っていたことを聞いた。それまで、どういう手順で本を手に入れたのかは、記憶に薄い。おそらく、友人などからの伝言、教科書にある文章などがきっかけとなって読書を始めたのだと思う。書評については、私が10代後半から刺激を受けていた旧友の言葉でもあって、以来朝日を中心に読んで本を求めるということが加わったように思う。
書評良し、本良し、という書評との交わりがほとんどであるが、そうでないこともある。10年くらい前だろうか、現東京工業大学教授の中島岳志氏が書評を担当していた。その当時、日曜日が待ち遠しいくらい彼の書評を楽しみにしていた。ところが、あるとき推薦本を購入したところ、残念ながら、その本はさほど心に残らなかった。私は、書評を切り抜いて買った本に挟んでおく習慣があり、時折その書評を読み返す。それでわかったことは、私は本からの引用文に惹かれたのに、実際は、中島氏が本の引用文の前後を脚色した、その文章の流れに魅力を感じたということだった。このことから、面白い書評は、必ずしも面白い本にはつながらないと知った。私個人は、ただ彼の文章を読みたかったということだ。
それまでも、本によっては途中で面白くなくなって、投げ出したくなることがあった。せっかく買ったのだから、とにかく読み通そうと、無理を重ねたことも多かった。ある時、知の巨人と呼ばれる立花隆氏が、つまらない本だと思ったら、人生のムダだから、すぐに読むのをやめるようにと何かに書いていたものを目にした。どちらかというと、几帳面に読んでいた私が、どれだけ立花氏のおかげで楽になったことか測り知れない。中島氏の推薦本も途中で読むのをやめて、しかも何だったかは忘れた。
本を選ぶにあたって、書評は重要なのだが、私には書評子の文章が好きだという結論である。そういえば、河合隼雄が紹介した児童書より、彼がその本について書いた文章の方が面白いと言っていた友人がいたことを思い出す。
元朝日新聞記者の河谷史夫氏、彼が新聞の書評欄を担当した頃は、もったいなかったけれど記憶にない。しかし今、ある月刊誌にエッセーのように連載している書評がある。たとえば、名づけが大事、ということについて、「無名の『吾輩』がいちばん有名な猫の世界とは異なり、人間世界にあっては名前が大事である」という書き始めは、静かで深い見識を想像してしまう。私は、彼の筆致が好きで、彼の本も愛読した。
こうして改まると、私を刺激するきっかけは、本も書評もその筆致によるところが大きいということだ。中島氏や河谷氏に惹かれるのは畢竟、好みの問題だろう。しかし、私は好みの問題として隅に追いやることなく、惹かれ続けてきた。いわば浅いつき合いより深いつき合い。書評子との出会いが、重宝した朝日を超えて、部屋の本棚やファイルを豊かにしてくれている。
二冊の本
2017年04月01日
毎年、映画評論をしている知人からもらう年賀状には、1年の間に作られた映画のうち、自薦のベストが挙がっている。今年は『ハドソン川の奇跡』であった。折をみて映画を鑑賞するつもりである。
さて、昨日とはちがう今日となるのが読書。私も知人にならって、映画ではないが、この1年のうち夢中になって読んだ二冊の本を紹介してみたい。
『鼻の先から尻尾まで -神経内科医の生物学-』 岩田誠
変わったタイトルのこの本、神経に関したことがこれほど面白い世界だったのかと、改めて神経内科学を学びたくなった書物である。鼻の先から始まり尻尾まで30の話が記されている。
タイトルが「鼻の先から尻尾まで」と名付けられた由来は、これが神経内科の診療範囲だということからであるらしい。一般には、人体の全てを表すときには、「頭の天辺から足の裏まで」という言い方をする。しかし、この表現では、人体の最先端と最後尾の診療を放棄することになると著者は言っている。そこで、このタイトルを理解するには、人体の感覚神経の皮膚分節を一見すればよいという。そして、それを補足するよう、ヒトが四肢動物として四つ足姿勢をとった絵が挿入されている。成る程、この姿勢だと鼻が先頭にあり、臀部が最後尾となる。ヒトの身体全体を、今の二足歩行だけではなく、進化以前の四つ這いの姿勢から見つめてみようというのである。歴史でいえば、今の時代を現時点だけ切り取って見るのではなく、明治、大正、昭和からの流れで捉え直すことなのである。医学書には、おそらくこの視点はない、と思う。著者は、色んな動物に言及もしながらヒトを説明している。
「或る日、なけなしの髪を洗い終えて鏡の中を見つめた」著者は、片眼をふさいでみる。すると、開いた眼の瞳孔が散大していることに気づく。そして、そのことは神経内科や眼科の教科書には書かれていないことに得意になる。しかし、対光反射の遠心路から出た線維は眼球に向かうが、それと同時に眼球には、左右の網膜から来る線維が入ってきている。それだから、片眼をふさげば光が減るのは当たり前で、小躍りするほどの発見ではなかったと、すぐさま訂正調の文章が続く。
しかし、著者はこの経験を簡単には捨てない。大学の研究者は教育者でもある。著者は、さっそくこのことを講義に取り入れた。学生に瞳孔径を測らせて、その変化を見させて、その理由を考えさせるのだ。何よりも自分の身体を観察することが臨床の基本だと学生に教えているのである。
著者は、頚椎、鼠径輪、肛門周囲の静脈叢、腰椎などは、ほとんどが二足歩行となったことと関連することによる構造欠陥であると指摘している。頚椎に至っては、神様の設計ミスのずさんさ、とまで言い切っている。ヒトが二足歩行し始めたとき、それまでに二足歩行をしていた恐竜や鳥類と比べて、脳みそが重過ぎた。そこに、神様の予想を裏切って寿命が延びたため、高々40年の耐用年数しかない頚椎椎間板の様々な疾病に悩まされることになった、と述べている。腰椎にも在るやはり同じくらいの耐用年数しかない椎間板。これらの構造欠陥を神様の失敗と著者は言う。この神様の失敗説に、腰痛持ちの私は納得した。著者も腰痛を経験したらしくて、痛みを起こさない予防策を講じている。すなわち、捻るな、担ぐななど幾つかを揚げている。これらは、私がこの数年で会得した予防策とほぼ同じ内容であった。
以上、内容の一部を紹介した。各ページ、各行に神経の説明、身体の観察、人間の観察が隙間なく書かれていて興味をそそられっ放しであった。ここで、ほんのわずかしか取り上げられなかったことが残念である。200ページに及ぶこの本は、これまでの臨床上の視点を大きく拡げてくれた。
『鹿の王』 上橋菜穂子
ずい分前から、私の娘に上橋菜穂子はいいよと勧められていた。娘に会うと何かと話題となる上橋菜穂子。昨年、『鹿の王』には、伝染病など医学的なことが書かれているよと言われ、それなら実益を兼ねて読んでみようと買い求めた。
これは、命と病に向き合った、大自然をバックにしたスケールの大きな小説である。大自然とは言っても、幻想的な架空の世界の話である。先ず帝国の侵略によって奴隷にされた主人公が登場する。囚われの身になった主人公のいる洞窟に、黒狼が侵入し、噛まれてほとんどの囚人が死亡する中でたった一人生き残り、主人公の生きる旅が始まる。一方でもう一人の主人公である医術師が、黒狼による病の原因究明に乗り出して話が展開する。
人の病を左右する場面では、身体の免疫学的反応が詳しく記されている。黒狼に噛まれて病を発症する民と、主人公のように発症しない民がいることが、この小説の一つのテーマである。文中には、たとえば、「毒を弱めた黒狼熱の病素を用いて、その病素に抗し得る力を人の身体に与える」「病素の活動を抑える力を持った素材を用いて」「感染者の身体が作っていた、病と闘う成分を精製した」など、免疫グロブリンやワクチンと思われる医薬品の精製などに言及していて、これらが話の進行の鍵となる。また、ある種の生物が重要な感染源となる話に及ぶ中で、免疫学的寛容を学んで理解が深まる個所もある。
一方で、このような医学的世界の話だけではなく、神がこの世を創ったなど、旧約聖書のような宗教的世界にも入り込む。また、「生きることには、多分、意味なんぞない」「家族や身内に感じる愛情もまた、生き延びるためのものだ」など、哲学的とも思われる世界もある。これらの多岐にわたる視点は、著者の幅広い教養があってこその内容である。
たまたま見たテレビで著者がこの小説に言及していた。彼女は更年期を迎えたとき、「あなたはもう結構です」と言われてしまったような気分になったという。そこから、ヒトはなぜ生まれ、なぜ死ぬのか、それを知りたいと思うようになったという。そして、そのことを追求して出来上がったのがこの小説である。「もう結構です」から小説が完成するまで、著者に浮かんだいくつもの問いや閃きがあった。それを明らかにするためのいくつもの歴史、医学そして生態学などの調査が行われ、それらが小説の中に散りばめられている。幻想的な架空の世界とはいえ、これらの丹念な調査に基づいて書かれているため、深みがある。
総じて物語は、免疫学から宗教的記述へ転じたと思えば、二人の主人公の登場をタイミングよく場面転換させ、興味の対象を次から次へと目まぐるしく変える。物語を覆う幻想性と正確な疾病の説明とは、一見矛盾するような事柄であるのに、何の抵抗もなく読み進められる。それを可能にしているのは、著者の知性である。
この本を読もうとしたきっかけは、娘に勧められて、しかも免疫学を扱っていたからである。しかし、想像も出来なかった幻想の世界にすっかり浸かり込んでしまった。あとがきに、医学に関する部分は、従兄の医師に監修してもらったとあった。さもありなん、医師としての興味も尽きずに、上下2巻、1000ページを超える物語を一気に読了した。
昔、人づき合いしないで読書ばかりしていると世界が狭くなるよ、と忠告されたことがあった。何をか言わんや。ここに紹介した二冊は、いずれも私にとっては、大きく視野を拡げる「別ぴん」な世界をもたらすものであった。
註
岩田誠『鼻の先から尻尾まで -神経内科医の生物学-』(中山書店 2013年)212頁
上橋菜穂子『鹿の王 上 -生き残った者-』(KADOKAWA 2014年)565頁
『鹿の王 下 -還って行く者-』(KADOKAWA 2014年)554頁
木の芽時に
2016年04月28日
春のある日、運転しながら思い返した。人間の身体を構成している細胞は、絶えず入れ替わって新しくなる。細胞は、60-70兆個あるといわれ、1年でほぼ新たになるといわれている。せっせせっせと細胞を入れ替える動物の営みを改めてダイナミックだと思った。
さて、道路沿いに群生して赤い新芽を出しているクスが、フロントガラス越しに視界に入った途端、紅葉だ、と見紛った。木の芽時には、心身の変調をきたすことがあるが、これは単なる錯覚だった。見事な色だ、と思いながら山々を見ると、シイが新芽を噴き出している。新芽に限らず、あちこちには、さまざまな花が満開だ。世の中、サクラ前線がニュースになるように、サクラは春の主役だ。しかし、クスもシイもどっこい、存在感がある。
生きるためであり、生きている証拠である細胞の入れ替えをする動物には、この季節の植物のような視覚に訴える見事さは、ない。見事な分、生きるすべを心得ているのは、動物より植物の方ではないかと愚考しつつ、生きとし生けるものへの畏れを抱く。この季節ならではの感慨である。
お蚕さま
2015年10月19日
昭和32年、私は父母に連れられて、群馬で生まれ育った私の祖母の一族をはるばる訪ねた。私たちは、既に亡き祖母の弟である私の父の叔父の家にしばらく滞在した。父の叔父たちは、家の二階で蚕を飼っていた。母の記憶では、群馬のどの家の二階でも蚕を飼っていたそうだ。群馬の人たちは、お蚕さま、と敬称を使って蚕を飼い、生糸の原料となるマユを作っていた。その様子は、子どもだった私の頭にいつまでも残った。おそらく、蚕を飼いたい、と私は父母にねだったのだろう。その年、小学生になり蚕を手にした私は、学校から帰ると、蚕の好物である桑の葉を取りに行くことを日課にした。
そんなことを思い出したのは、NHK大河ドラマの舞台が群馬となり、製糸業に力を入れている場面があったからである。ドラマの時代から昭和32年まで約80年、お蚕さまという敬称を当時使っていたことは、製糸業の尊さを引き継いでいた証であろう。しかし、さらに時を経た58年後のいま、群馬では、お蚕さまという敬称を日常的に使う人がどれだけいるだろうか。製糸業は言うまでもなく、産業構造は大変革を遂げた。
さて、昔読んだ寺田寅彦の随筆に、「文明の波が潮のように押し寄せてきて、固有の文化のなごりはたいてい流してしまった」という記述があった。これは、江戸から明治への変革の様子を大正10年に記したものである。明治維新は、おそらく日本中の人たちの生活を大きく変えてしまっただろう。そんな視点で、昭和32年頃群馬にいた人たちの営みの変わりようを思ってみた。寺田寅彦が記した変革があってから80年もの長い間、生糸の大事さは群馬に在り、私もその一端を垣間見させてもらった。しかし、昭和32年からこちら、潮のように押し寄せてきたものは、何だっただろうか。少なくとも、2年前に同じ群馬の地で私が見た光景は、ナシ園、いちご園、酪農であり、もちろん養蚕業ではなかった。
お蚕さまという言葉はおそらく朽ちた。しかし、この言葉には、私の個人的な懐かしさだけではなく、80年の重みがある。この言葉を元にして、新たな息吹を入れられないだろうか、とドラマを見ながら夢想した。
奥平康弘さんの文章
2015年08月01日
今年、国会に提出された安全保障関連法案が違憲であると疑われて、ほとんどの憲法学者が法案に異を唱えている。そんな中で、「私たちには憲法尊重擁護義務がある。100の学説よりも一つの最高裁判決だ」、さらに、「国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、自衛のための必要な措置が何であるかについて考え抜く責務があります。これを行うのは、憲法学者でなく、我々のような政治家なのです」と政治家も発言を重ねている。
この、政治家と学者とで異なっている意見をどう理解したらよいのか。私を始めとして、憲法を専門とせず、政治家ではなく、しかも提出された法案に不安を抱く人間に、指針はないのか。そう考えていたとき、一つの書物に出会った。先ごろ亡くなった憲法学者の奥平康弘さんが書いた、「憲法物語」を紡ぎ続けて、を読み通した。
裁判所か学者か、ということについて、奥平さんは、以下のように記している。長くなるが引用する。
「裁判所は、ある法律が憲法に違反するかどうかという裁判において、どのような基準や論理で、どの部分をつかまえて、これは違憲であるとか違憲でないとかいう司法審査の手法を明確に認識し得ていなかったのです。アメリカの勉強をすればある程度わかるかもしれませんが、急いで判決を出さなければならない裁判で、研究者がやるようなことをやれるはずがない。そうすると、自分たちの既存の知識を使って、まことしやかにと言っては怒られるでしょうが、論理を組み立てるしかない。」
これは、政治家と憲法学者が争っている今ではなくて、14年前の2001年3月に講演されたものを文章化したものである。研究対象をどう深めているかということと裁判所の既存の知識との違いがわかる。政治家と学者の意見に対する賛否はともかく、学問を侮ってはいけないということに改めて思いが及んだ。
先に引用した部分に、アメリカの勉強をすれば、と簡単に書いているが、他の文中には、アメリカ憲法一辺倒、とまで書いていて、アメリカ憲法についても相当な研究をしていたことがうかがい知れる。しかも、憲法について、むずかしいことを誰にもわかるように、やさしく述べている。また、学問としての憲法に近づくための挿話の数々。昔、私は研究することを早々と断念した。その私が述べるのもおこがましいが、読んでいて、もう一度研究をしたくなった。この本は、研究に一生をささげ続けたことがわかる文章で覆われている。
束の間の妄想
2015年07月17日
所用で出かけたときのことである。名古屋で新幹線に乗り継ぐため、自動改札を通った際、出てきた切符が行き先のちがう別の切符だった。私の次に通った人も別の切符が出てきたらしい。私の前に改札を通った人と私の切符が混ざってしまったのではないか、と咄嗟に判断して、急いで追いかけて呼び止めた。案の定、三者の切符が改札の中で入り乱れてしまったようだ。自動改札に切符を入れた時、前の人の切符はまだ機械の中に入っていて、私の入れるタイミングが早すぎたのかも知れない。しかし、このようなタイミングは、大量の切符をさばく機械の側からみたら、日常的なことだろう。それでも出てきた切符はまちがっていた。これは、機械の誤作動によるもの、と結論した。
今度は翌日のことである。まちがいは、年とともに身近なものとなる。所用を終えて帰る際に、1つあとの新幹線に乗ってしまった。座っている私に、そこは自分の席だと、あとから乗ってきた人に言われた。切符を見比べたら、列車番号がちがっていた。あちらがまちがっていると思って、あなたは別の列車に乗ってしまいましたよ、と親切心のつもりで話したところ、あなたこそまちがっている、と反対に言われてしまった。駅のホームに上がったところまではよかったのに、確かめもせずに乗ってしまったのだ。
そんなことがあって間もないある日、部屋でプロコフィエフの束の間の幻影を聴いた。不協和音が連続して交錯するなかで、突然鮮やかな色が見えた。一瞬、妄想ではないかと思ってしまった。そして、昔学生時代に精神医学の講義で、妄想とは誤った信念を持ち続けることだ、と聞いたことを思い出した。さらに、新幹線に乗ったことに思いが至る。そういえば、新幹線を利用して所用を済ませるまでは、機械が誤っていたと信じていた。そして、翌日も同じ座席番号の相手がまちがっていると信じた。
いずれも相手に非があると信じ込んだものだが、ふと、この信念も妄想ではなかったかと頭をかすめた。あわてて昔の講義ノートをひっくり返して、妄想の部分を確認したら、訂正不可能ということも特徴のうちの一つ、と書いていた。妄想ではないかと疑ったのだから、訂正不可能ではないなあと、この記述にやや安心した。しかし、たとえ機械が誤っていたとしても、誤った信念に結びつけてしまったのは浅はかだったと反省した。一方、妄想を抱くような自分ではないということではなく、妄想ではないことを見極めたことに妙に安心もした。まちがいが身近になり妄想にまで思いを致してしまう。それでも、学生時代に学んだことを引き合いに出すことを始めとして、まだ私に与えてくれる可能性を使い切りたい、と思った次第だ。
ところで、曲を聴いていたときに見えた鮮やかな色は、何とも不思議だった。このようなことがあるのだとしたら、妄想を予感して、束の間の幻影という題をつけたにちがいない。見えた色も、曲を作ったいきさつを推理することも、妄想ではないと思うのだが、さて。