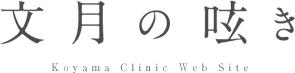健全なる肉体あればこそ
2025年11月30日
「健全なる精神は健全なる肉体に宿る」とは、ローマ時代に書かれた詩人の言葉である。広辞苑には、身体が強健であってこそ精神も健全である、とある。有名な言葉であるが、私は若い頃、その意味について感慨もなにもなかった。そして、ずっと意識にも上らず忘れていた大学在学中のある日のこと、同級生が何かの話の途中で、この言葉を持ち出した。すなわち、これは、健全なる肉体に宿るのが望ましい、ということなのだと、彼の解釈を述べたのだ。
望ましい、と付け加えるほどに、この言葉に深遠な意味が含まれているのではないかと想像して、畏れ多くなったことを覚えている。しかし、残念ながら、その本意を彼にたずねなかった。以来、私はこの言葉が浮かぶと同級生を思い出すという具合だった。彼は、哲学を他学で学んでから医学を志したという経歴を有していた。だから同級生とはいえ、数年の年配だったこともあり、私は一目置いていたのだ。
さて、病を得た3月からずい分と月日が過ぎた。外では、すでに色づいたカツラの落葉も半ば終わっている。身体の不調は、勝手気ままに過ごさせてくれない。しかし、その期間を、長かった、と過去形で綴ることが出来そうだ。ようやく症状が軽くなってきたからである。ただ、血液検査で炎症反応がまだ残っているから安心はできないものの、「復活」の兆しを感じるこの頃である。
この長患いのせいで、少なくとも創造的な生活は削がれた。ピアノは弾かなくなり、このHPもほとんど更新しなかった。また、夥しい数のメールを処理せずに、仕事の関係のメールも読まずにいたら、返事を催促された、というように塩梅が悪かった。それらのことを過去に追いやれそうないま、気分の赴くままに過ごしている。また、同級生が言った、健全なる肉体に宿るのが望ましい、という解釈は、全くの健やかではないいまのような状態もあるから付言したのだろうと、今更ながら蒸し返している。あと一歩、健全な肉体を所望できそうだ。
銀髪の老人 ー音楽鑑賞事始めー
2025年08月10日
細身に和服、髪はオールバックで銀髪。今は昔、東京は銀座、とある音楽喫茶店に入った時に見かけた老人の風貌である。座っているその御仁のテーブルには、大きな楽譜が置かれていた。大きさからしてフルスコア、すなわち総譜だと思った。フルスコアは、曲全体を俯瞰できるものの、なかなか愛好家は所持しない逸物である。そんな楽譜を見ながら、彼は何と手で指揮を執っているではないか。曲はブルックナー。この姿に心を奪われた私は、いまとなっては何のために銀座に出向いたのかは思い出すことが出来ない。
この頃と相前後して、私は楽譜を見ながら音楽鑑賞するようになった。いや、この老人に刺激されて、鑑賞するに足るには楽譜を見ようと思ったのかも知れないが、自分のことながら定かではない。しかし、楽譜を手にするようになってからというもの、同じ曲でも演奏者によって異なる表現のちがいを聴くのが、俄然面白くなったのだ。たとえば、ほとんどの演奏者が音を切れ目なく演じている個所を、ある人は次に進む前に、明らかに音の連続を断っているのである。楽譜では、前者にフェルマータ(音の延長記号)、後者に八分休符が書かれた或る個所である。私の知っている限り、現在ほとんどの演奏者は、前者を長く伸ばし、その音が消え入る前に、八分休符でひと呼吸置いて、結果的に音の切れ目なしに次に進んでいる。ところが、ある人は、長く伸ばした音が消え入って、それから八分休符から始めるので、音の連続性がなくなっているのである。
ここにあるフェルマータは音を伸ばすだけではなく、辞書で引くと、音を伸ばし拍子の運動を一時停止させる指示、と書かれている。この一時停止をどう解釈するかで、流れは大きく変わることが想像できる。それだけではない。後者の八分休符をどう解釈するか、その重みを感じるか否かも、流れを左右する。私は、この音の連続性を断った演奏を初めて聴いたときには、その斬新さに驚いた。以来、好んで繰り返し聴いたものである。
この演奏は、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮のベートーヴェン交響曲第5番。この第5番をいまはほとんど聴かなくなったが、昔からクラシック音楽入門曲として知られる。私も例に漏れず、10代、20代の頃はよく聴いた。改めて聴き直してみると、フルトヴェングラーに限らず、トスカニーニ、メンゲルベルク、アンセルメなども音の連続性を断っている。彼らはどちらかというと、古の指揮者である。しかし、フルトヴェングラーの断ち方は、他の誰ともちがうのである。すなわち、音を断ってから、次が果たして始まるのかどうかと「不安」を誘い、無音の音に集中せざるを得なくなる。
第5番の楽譜を書棚から取り出してみると、高校生の時に買ったものだった。全音楽譜出版社のビニールで装丁された年代物である。ということは、銀座に行く前から楽譜を手にしていたのだ。蛇足ながら、イタリア語であるフェルマータは、バス停をも意味している。すなわち、ここは連続性を断った解釈が、ベートーヴェンの意図したところだったのではないかと愚考する。
折りに触れて思い出す銀座の老人。咄嗟に当時は、私が知らない指揮者だったのではと想像した。とにかく、彼はフルスコアを携えていたのだ。しかし、よくよく考えると指揮者が他の指揮者の演じた再生音を聴くために、わざわざ銀座に行かない。いや、反対に指揮の参考にすべく銀座まで赴いたのかも知れないとも思う。いずれにしても、遠い昔のことで、指揮者だったかどうか判る手立てはなくなった。それでも、いま在る私の音楽鑑賞をかたどる一つが、銀座でのひと時だったと思う次第である。
後期高齢者
2025年07月05日
後期高齢者となった。医療制度を新たにするために命名された後期高齢者。その言葉の響きに慇懃無礼な差別用語のようだと独り言ちていたのが、ふた昔近くの前の平成20年だったとは。改めて、流れるが如くの時節を思う。あっという間にこの年齢になったと、圧倒的な思いである。
平成20年、後期高齢者医療制度が始まった。これは、75歳以上の人を対象とする心身の特性や生活を踏まえた独立した医療制度である。詳しくは成書にゆずるが、加齢の影響などで持病が増える世代を後期高齢者として、この年度より、その医療を社会で支えることになった。
この2,3年、私個人は、それまでの年齢では、ほとんど縁のなかった複数の診療科で診察を受けるようになった。それが年々増えていまに至っている。当初は、高齢者になると忙しいなどと、半ば冗談ごとのように言っていた。しかし、複数科を受診することは、本当に忙しいことで、もう冗談など言っていられなくなった。
その診療の実態はというと、いまの病態はどういう状態で、どう健康体に影響しているか、選択できる治療はどうなっているか等など、専門科で診療している医師と話が出来るという、これまでにない時間を享受できている。それにしても、各々担当医師は、私の若い頃とはちがって診断機器を大いに駆使している。だから、こちらから聴きこまなくても、私に十分な情報を伝えてくれることが多い。ただし、医師各々のきめ細やかさについては、後日触れられれば触れてみたい。
私の場合、後期高齢者になる前に、このように診察を受ける機会が多くなった。さらに後期高齢者となると、拍車がかかることが予想される。もっと忙しくなるのであり、歳など取っていられなくなる。ボーっと生きているんじゃないよ、とチコちゃんに叱られそうで、新たな冗談ごとを言う状況が多くなるかも知れない。
医師と患者は、一対一対応であるが、患者の側からは医師と多対応、複数の医師と接することとなり、大げさに言えば、生活の仕方を変えなければならなくなる。実際に患者となって、私は生活が変わったように思う。そして、患者を体験した医師として、多くの医師との対応を余儀なくされているのが高齢者だということを踏まえて診療に当たることを強く思うようになった。なかなかに忙しいではないかと、後期高齢者になった最初の感想である。
病んで考えたこと
2025年06月23日
病を得て3カ月余、未だすっきりとはせず、主治医からはあと2ヶ月は治療を続けるよう指示をいただいている。
この間、診療は出来るものの、仕事を終えたときの倦怠感が強い。それもそうだ。短期間に4キロも体重が減ったのだから、肝心なところに力が入らず、無理がいくのだろう。それでも、日にちとともに症状が軽くなるにつれて体重が少しずつ戻った。症状が軽くなると、気持ちも前向きになる。ところが、日によって無くなったと思った症状が頭をもたげるのである。そのたびに、ぶり返したのではないかという不安が増し、なかなか普段のように前向きにはならない。そのうえ、やらなければならない股関節のリハビリが滞ってしまって、関節から下の部分の痛みが増している現況である。病気一つ加わっただけで、このざまである。
さて、世の高齢の患者さんは、いくつも病気を抱えていながら、日常をこなしている方が多い。特に、私より半周り(6年)以上年配になる80代の患者さんは、80の大台に到達して吹っ切れたのか、頓(とみ)にお元気である。つい、彼我の差に思いが至ってしまうある日のこと、無病息災という言葉が浮かんだ。これは字の通り、病気をせず健康であることをいう。実際に年を取ってみると、無病とはなかなかいかないことは自明のことである。それだからか、一病息災という言葉もあって、こちらは、持病が一つくらいあったほうが健康に注意することとなって、返って長生きする、というような意味のようだ。うーん、病を養っているいま、無病息災も一病息災も、いまの私にはどうにもそぐわない言葉だ。思えば、還暦の頃に腰を痛めてからというもの、腰をかばう生活を余儀なくされている。さらに、眼科、外科、泌尿器科と診察機会が増えた。こうなると、一病ではなく多病。しかし、こんな言葉はない。近ごろEテレの番組で、未病息災の文字があった。これも辞書には書いていないから、どういう意味かわからない。未病息災より、多病息災のほうが表そうとする意味がわからないでもない。しかし、そんなことを話題にしたところで、同年齢ではまだしも、まず普遍性はない。
まあ色々と綴ってみたものの、この歳になってわかったことはいくつかある。歳なりに達観したことは、世間の色んなことが、どうもこの歳には合わないことが多いということである。たとえば、無病息災、一病息災という言葉。これらは、おそらくずっと昔から言われてきたことで、しかも言われ始めた頃は、いまのように平均寿命が80歳台ではなく、ずっと若かったと思うのだ。そうすると、結局これらの言葉は、もっと若い世代が対象なのだ、ということなのである。
「無病」も「一病」も、私自身がこのことを論ずるには、もう相応しくない年齢になってしまった。何にせよ、いまは次から次へと病気が襲ってくるのである。前述した80代の患者さんたちは、おそらく「多病」と上手く共存している。私も病膏肓に入るばかりではなく、80代に見倣いたいものだ。
「人知れぬ涙」
2025年03月04日
この表題は、半世紀前に私の友人が、とてもいい歌手が歌っていると知らせてくれた曲名である。すなわち、ドニゼッティ作曲の歌劇「愛の妙薬」のなかのアリアであり、歌手はティト・スキーパ。その際彼の歌を、すごい声?とろけそうな声?死んでしまってもいいくらい?いや、正確な言葉は残念ながら忘れたが、友人は最大級の誉め言葉をもって、勧めてくれたのである。
そのスキーパの音源を久しぶりに取り出して、「人知れぬ涙」を聴いた。始まるや否や、かつて聴いたときの思い出が一気によみがえった。何もかもがとろけてしまうような声、包み込まれるような声、弱く歌う歌い方、その弱音を長く保つ歌い方の魅力等など、いくら記しても記し足りないという思いだ。いや、歌の全貌を正確に記すことなど出来ない。ついでに、オー・ソレ・ミオ、サンタ・ルチア、ラ・クンパルシータなど有名な曲を含めて、多くの歌を聴き通したのがつい先日。聴き終えて、昔その声をそっとLP棚にしまっておこうと思ったことを思い出した。
「人知れぬ涙」は、1929年に録音された。それにしても、この音源をよく残してくれたものだ。スキーパは、1889年(明治22年)に生まれ、1920年代から1930年代にかけて活躍した。ちょうど大正から昭和の初期にあたる。スキーパの声、歌を表現するには、言葉に特殊な文言が要るに違いない。私には、それを見つけられないと今更ながら思う。肺でガス交換し、気管支、気管と通った空気が声帯を震わすことに、スキーパは他の人と何を違えているのだろうか、と記したところで、何の解釈にもならない。
そういえば、今年は昭和100年にあたる。スキーパが活躍してから約100年ののちに、彼の声を享受できるしあわせ。こんな私の文章などすっ飛ばして、彼の甘くてとろけそうな声を、とにかく聴いてください。
リヒテル、モーツァルト
2025年02月12日
朝、FM放送をつけてみたら、シューマン作曲の幻想曲が流れていた。和音の切れ味、先へ進む、その進み方、速いパッセージほど無遠慮に聴こえることなど、その演奏の仕方からピアノはスヴャトスラフ・リヒテルだろうと思いながら聴いていた。案の定、曲が終わってから「リヒテルでした」とのアナウンスがあった。偶然のことながら、私はその前日にリヒテルがモーツァルトのピアノ協奏曲第27番を弾いたライブ録音を聴いていた。まるで誘(いざな)われた如くに、彼の世界に久々に連日浸かったのである。
聖域という言葉がある。広辞苑を引くと、神聖な地域、犯してはならない区域などとある。モーツァルトの最晩年の曲は、その言葉を被せたくなるくらい、曲に透徹した響きを感じる。最後のピアノ協奏曲である第27番は、そのうちの一つ、いや、この曲があるからこそ、この言葉が自然に湧き出てくるのだ。
昔、アシュケナージが来日して、この曲を赤坂のホールで聴いた。そのときの感想を書いて、いまは廃刊となったレコード芸術に投稿したところ、掲載してくれたことがあった。そこで触れたのは、第2楽章の最後のほう、第74小節目と76小節目にある一オクターブ違えた同じb♭の奏で方であった。深まり、音符が少なくなり、静かになり、というパッセージ。私は、この感想文に、音が鳴るのではなく、生起している、と書いた。
この部分を、このたび改めてリヒテルで聴いた。しかし、アシュケナージの演奏とは違って、生起している、という文言は当てはまらなかった。聖域という言葉も被せられない。聖域というより、あらゆるところから音が次から次へと創られる。聴き手は、次の音がどう演じられるのだろうかという期待を抱かせられたのである。これは、リヒテルを聴くといつも抱くことである。どんどん進む、というと語弊があるかも知れないが、最晩年などと言って、特別視するのではなく、ここの音にも弾き手固有の響きがあることをわからせてくれる、といったらいいのかも知れない。
最終楽章も、一気に弾いてしまって、最後の方のソロで弾く部分は虜になってしまうくらいのエネルギーがあった。この演奏は、フィレンツェの会場で演じられ、指揮はリッカルド・ムーティ、オーケストラは地元フィレンツェの管弦楽団のようだ。CDはイタリアからの輸入盤なので、仔細はイタリア語で書かれていて、私にはわからない。しかし、曲が終わった途端、割れるような拍手が延々と続いた。そして、あろうことか、最終楽章がアンコールとして再演された。
来日したリヒテルを初来日から、何度か聴きに行った。そのたびに、音楽の「深み」を覗かせてくれた。それは、聴き手に興奮、沈潜など、ひと言では済ませられないいくつもの形容句が浮かんでくる演奏であった。フィレンツェの聴衆がどんな感想を抱いたのかは、割れんばかりの拍手が表わしていると思ったCD記録であった。
景観と利用
2025年01月09日
我が家から国道を南に進むと、吉野熊野国立公園に指定された七里御浜が県境まで約20キロにわたって続く。外海が普段はおとなしく波を打つ。ただ漁港にはなり得ず、寿司屋は勝浦などまで仕入れに行くと聞いた。また、少なくなったとはいえ、御浜小石は砂利浜に混じって見られる。そして、松の群生。こどもの頃、私は松林の中で野球をした。残念ながら松枯れによってその本数は激減してしまった。斯様に少しずつ様相は変化するものの、海の青さ、小石の白、松の緑の彩りは変わらない。国立公園と改まるまでもなく、歴史的景観を形作る自然がここに在る。
あ?何だこれは?取り返しがつかないではないか、と嘆息をもらしたのが30年くらい前だった。久々に見た御浜には、道路に隣接して、50-100メートルくらいの長さを占有したヤシの木が林立していた。以下に、私の淡い、不確かかも知れない記憶をたどって記す。すなわち、当時ヤシの木を植えたことについて、県職員がここにハワイをイメージして、七里御浜に別の景色を提供したかったと、何かで述べていた。ハワイ?私が嘆息をもらしたのは、地方には地方の歴史的景観があり、それをよしとして国立公園に指定するのだろうと、漠然と思っていたからである。白砂青松。ヤシの木は、当地の歴史にそぐわない。
さて、国立公園に関係して、自然公園法という法律が作られている。そこには、自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図る(以下略)と書かれている。このような文言があれば、ハワイをイメージして利用を増進することはたやすいことなのかも知れない。実際、法律に則ってヤシの木を植えたと思われる。ただ、国が管理する国立公園の整備陣頭指揮を、県職員が進めたことに整合性があったのかどうか、私にはわからないまま、いまに至る。
いま、このヤシの木を植えた個所は、七里御浜ふれあいビーチと称されているようだ。インターネットには、「まるでハワイな気分を楽しめる、海沿いの映えスポット」と書かれているサイトを始めとして、この個所を紹介するいくつものサイトがあり、多くの人がここで過ごしている様子がわかる。「歌は世につれ、世は歌につれ」。人の意向で、世の中は変わる。七里御浜で触れあい楽しむことも変わってきている。私は、時代が変わることに寛容であるつもりで禄を食んできた。そして、金子みすゞの、みんなちがって、みんないい、に共感を覚えた。しかし、どうも私には寛容さがないのかも知れないと思うこともある。というのも、何年経っても、自分を赦そうとしても、「七里御浜にヤシの木」は、私には、寿司にガーリックシュリンプはよく合うと言われたような気分が拭えないからである。
この気分は私の懐古ばかりではあるまい。これまで、私はここに一度も足を踏み入れていない。
新型コロナ感染症と怖さ
2024年12月16日
NHKで、2回にわたって新型コロナ感染症に対峙した2つの医療チームの働きを取り上げていた。
1回目はクルーズ船の中で集団感染した人たちを治療した災害派遣チームの葛藤の記録。本来、災害に派遣されるチームが、船内が災害でもないことに加えて、感染の危険を伴いながら仕事を進めるというこれまでに例のないことを報じた。2回目は東京に第1波が押し寄せた際の医療従事者の闘いの記録である。ここでは、ある妊婦が感染し、帝王切開してから、意識がなくなり危険な状態になったことを取り上げた。ともに未知のウイルスによる感染に対して、前例のない治療を余儀なくされた医療チームが乗り越えたことの記録であった。
それから4年余経ったいま、新型コロナウイルスに感染しても、ウイルスが変異を繰り返したことによると思われる弱毒化された状態となっていて、当初のように重症化することが少なくなっている。それは、番組でも第1波では感染すると致死率が5.34%にも上ったのに対して、第6波から第8波では0.11-0.18%と少なくなっていることを示していて、変化は明らかである。
さて、この5.34%の致死率となった第1波。これは、20人感染すると1人亡くなる数値である。当時、役者の志村けんさんが亡くなったこともあって、恐れはピークに達した。その後、感染者が急激に増えて、当地でも多くの人が感染した。数字の上では致死率が徐々に少なくなっているものの、第1波の衝撃が尾を引いていた。そんな中で、当院にも感染を疑ったり、心配したりした人が、いわゆる押し寄せてきた時期があった。私は医師とは言え、患者さんに相対することが怖かった。そして、診察しながら、感染防御をすでに受けたワクチンに託する気持ちになったことを覚えている。
そんなことを思い出したのは、NHKの番組の途中で、クルーズ船に乗り込む前の医師が「怖い」と言っていたからである。その医師は、怖いけれど「背負わなければならない」「リーダーの役割の一つ」と述べて、行動に移したのである。私も怖かったけれど、来られた患者さんを、何故だか拒まずに診察を進めた。それだから、テレビで述べていた「背負わなければならない」という言葉に共感を覚えたのである。
ひとは、突然身に降りかかった非常事態に遭遇すると、何にも超越し、自然に湧いてきた勇気ある判断が瞬時に芽生えることがあるのかも知れない。そのように思わないと、怖いことを前にして、拒まずに行動したことを説明できないのである。2回目の番組で、東京の医師が、「生と死の究極のところに立たされて、自分の在りように大きな影響を与えた」と述べていた。病院で先端医療に従事する医師と、私のような開業医とでは、同じ職業と言えないくらいの業務の差がある。しかし、行動の始まりは同じだと思いながらの番組視聴であった。
100年
2024年11月13日
過日、母が100歳の誕生日を迎えた。その翌日、市役所課長さんと社会福祉協議会会長さんがお祝いに来て下さった。「人生七十古来稀なり」、その古希を30年も上回ったのだから、そうそう万人が到達できる年齢ではなく、身内ながら、祝っていただくことの稀有さ、ありがたさをそばで感じていた。このところ母は、100歳に自分がなるなど信じられないこととよく言っている。そんな母が、祝いの席で長寿の秘訣は何かと問われ、毎朝野菜を食べていると答えていた。
秘訣とは、奥の手や奥義といわれることであり、何やら字の通り秘密めいたことである。秘密であるかどうかはともかくとして、最近母と朝食の際に、家では野菜をずっと多く摂っているが、毎日摂り続けたら良いと話し合ったことがあった。野菜を摂る効用は言うまでもない。それに加えて、直近の朝の話もあって、口をついて出たのだろう。
さて、当の本人も不思議がっている100歳到達。市役所や社協の方だけではなく、そばにいる私だって、何故長生きできるのだろうと思うのである。それでも母と生活を共にしていると、長生きに資すると思われる幾つかの生活行動が浮かぶ。すなわち、母は、暑さ寒さに殊の外敏感なようだ。たとえば私が、風が吹いていると思っていると、横で「寒い」と言葉を発する。自然の変化より体感の変化に敏いのだろうと思う。そのことは、風邪を引くなど、身体への侵襲を防ぐことになり理にかなってもいる。また、人と話すのが好きである。「電話いのち」という言葉が相応しく、少ない範囲ではあるものの社会性が電話を通して保たれている。膝痛で行動制限があるにしても、携帯があれば事足りるのである。
以上、少しだけ例を挙げてみた。何だ、そんなことが長寿に与るのなら簡単なことだ、と思うことばかりである。しかし、このようなことが100歳まで到達することに必要でも十分でもないことは想像できる。野菜を多く食べる人は数多いる。身体が感じやすい人も、話し好きな人も特殊ではない。長寿の条件を、母を例にとってみても簡単には糸口が見つからないことはわかった。考えてみると、人の細胞は約60兆個あるといわれ、それらを何十年も統御しているのだ。改めて細胞の数を想像しながら長寿を俯瞰すると、さらに簡単ではないと思い知らされそうである。
長生きの秘訣は、との問いかけを機に少しだけ思いを巡らせた。そばで母を見ていても、がんばって100年を生きた、というような意思は持ち合わせていないと思う。自分のことを先ず考えながら、気がついたら100年経ったというような具合なのだろうと思う。秘訣もただ、身体によくないことはしないという程度のことだと私は思う。おそらく、100歳になった多くの人も、がんばって100年生きる、という人はあまりいないのではないだろうか。ただただ100年が過ぎたというおおまかさにあふれることしか浮かばない。周りの人に祝っていただくなかで、毎日を共にしている私のありふれた感想である。
診療、年齢そして年相応
2024年10月06日
数年前のことである。私は、昔自分が若いときに当時年配だった患者さんが訴えたことを、若さゆえにきちんと聞いてあげられなかったことをHP上に書いた。それは、自分が年を重ねて身体の不具合を自覚して初めて、訴えていたことがおぼろげながら、ああそうだったのかと思ったことから、比べるため敢えて昔のことをもちだしたのである。
私は、数年前のある時期から、年配の患者さんと年齢が近いと感じるようになり、若かった頃とはちがう関係になったと改めて感じた。すなわち、年を重ねたことにより、診察室では、自分が体験しつつある身体の不具合を基にして応ずるということが診療に加わった。
さて、年を重ね、それに伴って身体も変わることは述べた。それは、静かに、あるいは急に変わることがあり、しかも、一つではなく幾つもが襲ってくる。数年前までは、運動器官と感覚器官の不具合によって、行動制限を余儀なくされた。腰痛、足のしびれ、視力低下などがあるものの、ある程度限られていた。それが、このところ、消化器、循環器、泌尿器と次から次へと加わり、大腿骨など手術を勧められる事態なのである。しかし、本当に幸いに、予後(見通し)が悪くなく、無理をしなければ、何とかなる現状におさまっている。それでも、これまでにはなかった通院、相談に時間が割かれてしまう。静かな余生などという境地になるのは、いつのことだろう。身体の不具合が複合的に襲ってくるいま、ひと言でいうと、忙しい。
過日、敬老の日を迎えた。その日の天声人語には武者小路実篤の名言を引用している。「真から本気になって生きてみたい」「人生は楽ではない。そこが面白いとまあしておく」などの文言を眼にしていたら、つい、ゆとりのない私の性分と比べてしまった。そして、天声人語子は、「自らの老いもまた、しずかに見つめてみたい一日である。」と結んでいる。この人は、新聞社社員で50代か。私が50代の頃、老いを静かに見つめていたかどうかはともかくとして、人それぞれだと改めて思った次第である。