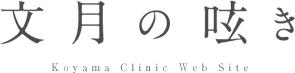時世の粧い
100年
2024年11月13日
過日、母が100歳の誕生日を迎えた。その翌日、市役所課長さんと社会福祉協議会会長さんがお祝いに来て下さった。「人生七十古来稀なり」、その古希を30年も上回ったのだから、そうそう万人が到達できる年齢ではなく、身内ながら、祝っていただくことの稀有さ、ありがたさをそばで感じていた。このところ母は、100歳に自分がなるなど信じられないこととよく言っている。そんな母が、祝いの席で長寿の秘訣は何かと問われ、毎朝野菜を食べていると答えていた。
秘訣とは、奥の手や奥義といわれることであり、何やら字の通り秘密めいたことである。秘密であるかどうかはともかくとして、最近母と朝食の際に、家では野菜をずっと多く摂っているが、毎日摂り続けたら良いと話し合ったことがあった。野菜を摂る効用は言うまでもない。それに加えて、直近の朝の話もあって、口をついて出たのだろう。
さて、当の本人も不思議がっている100歳到達。市役所や社協の方だけではなく、そばにいる私だって、何故長生きできるのだろうと思うのである。それでも母と生活を共にしていると、長生きに資すると思われる幾つかの生活行動が浮かぶ。すなわち、母は、暑さ寒さに殊の外敏感なようだ。たとえば私が、風が吹いていると思っていると、横で「寒い」と言葉を発する。自然の変化より体感の変化に敏いのだろうと思う。そのことは、風邪を引くなど、身体への侵襲を防ぐことになり理にかなってもいる。また、人と話すのが好きである。「電話いのち」という言葉が相応しく、少ない範囲ではあるものの社会性が電話を通して保たれている。膝痛で行動制限があるにしても、携帯があれば事足りるのである。
以上、少しだけ例を挙げてみた。何だ、そんなことが長寿に与るのなら簡単なことだ、と思うことばかりである。しかし、このようなことが100歳まで到達することに必要でも十分でもないことは想像できる。野菜を多く食べる人は数多いる。身体が感じやすい人も、話し好きな人も特殊ではない。長寿の条件を、母を例にとってみても簡単には糸口が見つからないことはわかった。考えてみると、人の細胞は約60兆個あるといわれ、それらを何十年も統御しているのだ。改めて細胞の数を想像しながら長寿を俯瞰すると、さらに簡単ではないと思い知らされそうである。
長生きの秘訣は、との問いかけを機に少しだけ思いを巡らせた。そばで母を見ていても、がんばって100年を生きた、というような意思は持ち合わせていないと思う。自分のことを先ず考えながら、気がついたら100年経ったというような具合なのだろうと思う。秘訣もただ、身体によくないことはしないという程度のことだと私は思う。おそらく、100歳になった多くの人も、がんばって100年生きる、という人はあまりいないのではないだろうか。ただただ100年が過ぎたというおおまかさにあふれることしか浮かばない。周りの人に祝っていただくなかで、毎日を共にしている私のありふれた感想である。
ハチ退治
2024年08月26日
先日来、毎日庭木に水やりしている。猛暑に加えて、日照りが続いたことで、サザンカが枯れかかってきたからである。ところが、水やりしていると、ハチがブンブンと飛んでくるのだ。以前、カシノキやキンモクセイのてっぺん近くに巣を作っていたことがあったから、上の方にまた作っているのではないかと、恐る恐る首を伸ばして探した。しかし、どうしても見つからず、水やりのたびに怖い思いをしていた。
ある日のこと、ふと低木であるサツキを、首を縮めて見たら、立派な巣があるではないか。道理で、水やりしたら騒ぐはずだ。さて、退治してもらうにも、庭師さんは来てもらったばかりで、お願いしにくい。そこで、市役所環境対策課に電話してみた。そうしたら、75歳以上の市民だったら援助するが、75未満なら防護衣を貸し出しするので自分で退治して、ということだった。防護衣だけだなんて、埒が明かないから、思い悩んだ末に、同級生の友人に相談してみた。ありがたいことに二つ返事で引き受けてくれたのである。
友人は、防護衣に身を包んで、サッとスプレーを巣にひと吹きして、あっという間に完了。他の個所のサツキにも別の巣があり、こちらも退治してもらった。ありがたかったことは言うまでもない。彼は、仕事柄ハチの巣に何度も遭遇するのだろう。その手早さは見事であり、その姿は自然体であった。そんな短い時間のなかで、彼の存在がやけに大きかった。彼とは、小学生の時に近くの川にウナギを取りに行くなど、共有した時間が多かった。その後、年を重ねてそれぞれ進む道はちがってしまったものの、兎にも角にも半世紀以上交流が続いている。
彼がハチ退治する立居振舞に、ふと、「餅は餅屋」という慣用句が浮かんだ。しかし、そのようにして言葉を使えば説明できるわけではないことも思った。そして、私とはちがった進む道を歩んでいるなかで会得したのであろう存在の「大きさ」をしばらく想っていた。ヒトは何事によらず反復することで身につける。身についたものは常に大きいか。そうではないだろう。ハチに刺されるという危険を冒して対峙していることが、大きさを生じるのか。そうではないだろう。昔、彼とウナギ取りしていたとき、彼は川の中にあったガラス瓶のかけらで足を切った。私は彼を背負って家まで連れてきた。幼かった頃から、いまに至る時間の流れと、ハチ退治している彼のいまを鳥瞰した。そして、一筋縄ではない過去からの集積が浮かび、一瞬にして大きさを感じたのである。
ハチ退治の顛末は以上である。蛇足ながら、彼は、ハチがこんな風に低木に巣を作るなど、あまり見かけたことがない、何か天変地異の前兆ではないだろうか、と発したことが気になっている。こればかりは、彼の「大きさ」と無縁であって欲しい。
懐かしい道
2024年07月14日
昨年末、奈良の山道の一部が崩落した。崩落の規模の大きさに加えて、地質調査の結果、深層崩壊の危険性があることから、長らく通行止めとなっていた。この道は、大阪を始めとした関西圏に行く縦断最短路であり、よく利用していた。ドライブが好きな私には、無数のカーブを用意してくれてもいる。しかし、通行止めの間は、県北部を横断している高速道路を利用せざるを得ず、その都度、約90キロ余計にドライブさせられるのである。
それが、崩落して半年後の先月末に仮の橋ができて、やっと交互通行ではあるものの、縦断できるようになったため、さっそく通ってきた。半年ぶりの道路、半年ぶりの景色。まるで旧い友に出会ったような感慨を抱いた。それもそうだ、私はかれこれ20年余、この道をドライブしていたのである。しかし、ここは2級国道であり、整備の点で1級国道より残念ながら劣っていて、至る所に劣化した「あかし」が露わになっている。このあかし、すなわち舗装の継ぎ目の段差や浅い穴ぼこ、これらを私は場所も数も覚えていた。数10キロにわたって、ほとんど覚えていた。それは、まもなく段差がある、身構えておかないと、という具合に。クルマが揺れるたびに、懐かしいという思いに満たされた。そのうち、旧い友という感覚を超えて、路面をいとおしく感じるようになり、何ともハッピーな気分で駆ったのである。この、道とクルマとの関係を誰にも感じて欲しくないという独占欲までもたげてきた。これは、思ってもみない自分の内の変化で、段差も穴ぼこも擬人化してしまった。しかし、この気分も、何故だかわからないが帰り道には失せていた。懐かしさは微塵もなく、半年前までと変わりなく、ごく普通のドライブ時間を過ごしながらの帰宅であった。
話変わって、メンデルスゾーンの音楽劇で知ったシェークスピアの喜劇「真夏の夜の夢」のことである。ここでは、森で会おうとする男女がいて、妖精が魔法を使ったり媚薬を使ったりして、劇が進行する。さて、劇のように真夏ではないし、夜に森に入ったわけではないものの、梅雨時に私は、久しぶりに勝手知ったる山道に入った。そして、まさかのハッピーな気分を味わった。そう、まさか妖精が魔法を使って、段差や穴ぼこを工夫したわけではあるまいに、そんなことを連想させられた。ドライブでしか得られないひと時であった。
相撲と習慣
2024年03月30日
大相撲春場所で110年ぶりに新入幕優勝を果たした尊富士。その快挙のニュースも一段落したこの頃である。優勝に酔ったからなのか、この数日、テレビをつけても大相撲の中継はなくて、ああ、終わったのだった、とたびたび確認する夕方のひと時である。終わってから、こんな風に後を引くことは、これまでなかったように思う。私には、場所中から存在感の大きな新入幕力士であった。その実力の分析は、専門家に譲る。
さて、力士は仕切りを重ね制限時間になると、呼び出しからタオルを渡されて、顔や身体を拭う。その拭い方は十人十色であり、力士一人一人に特徴があることが一目瞭然である。取り組みが始まって何日目だっただろうか、尊富士のタオルの扱いに目を見張った。彼はタオルを使ったあと、そのタオルを何と、ていねいに二つ折りにし、さらに折って小さくしてから呼び出しに返していたのである。ほとんどの力士は、タオルで拭った後はそそくさと、そして、人によってはぞんざいにというと言い過ぎだが、拭いたまま呼び出しに返して、すぐさま取り組みに集中している。
力士に限らず、ひとは生活の決まりきった行ないを、親からのしつけなどから習得する。彼の「タオル折り」は、しつけられたからなのだろう。何をどうしつけられ、「タオル折り」になったのか、ということはさておき、折ることが勝負に集中する一助となっているが如くの所作なのである。さらに、折るから勝つ、とあり得ないことまで想像した。私は、その習得した過去にも思いを馳せながら、毎日みていたら、あれよあれよという間に、大鵬の新入幕からの連勝記録に並んでしまった。
優勝を決めてからテレビの画面では、青森の実家の祖父が、「ほっぺにチューしたい」と満面の笑顔を振りまいていた。その笑顔と「タオル」とが重なって、家族の皆さんと彼の勝負強さとがさらに重なってみえた。もちろん精進の上での優勝にちがいないものの、育まれた習慣も力士の強さに一役買っていると、私は確信し、「巨人、大鵬、卵焼き」世代には、得も言えない記録を目の当たりにした春場所であった。
偶然の一致
2024年01月28日
フランスに34歳という歴代最年少の首相が誕生した。それ以前、この国では現大統領も39歳で就任している。若いと思いつつ他の国に目を向けると、ニュージーランドでは最近まで37歳で首相になった人が、そして、フィンランドでは34歳で首相になった人が活躍している。それ以外の国を調べていないものの、3か国では若さが政治を席巻しているという感想だ。
フランスでは、伝統的に若い人が国のトップに就いているかというと、そうではない。歴代の大統領の就任年齢は、6代さかのぼってみると、若い人で48歳、ほとんどが60歳代で、70歳代で就任した人もいる。フランスの過去を調べてみた限りでは、彼我の差はないようである。ましてや、まもなく行われるアメリカ大統領選挙に立候補しようとしている人は70代と80代だから、若い政治家が統治することは、そのような国もある、という程度のことなのかも知れない。
それにしてもと思う。過去にさかのぼると、フランスと我が国とでは差がないものの、いまの彼の国のように30歳代の為政者が我が国にも出現するようになるのだろうか。いや、国の政治を任せるにあたり、年齢で区切ることは適当ではないかも知れない。
と、ここまで書いたまま、事情があって中断していた。その数日後、朝日新聞の天声人語に、「政治家にとって年齢はどれだけ重要なのか。」という書き出しで、アメリカ大統領選挙、フランスの34歳の首相を例に出している。そこで、若いという年齢ではなく、「大事なのは力量」だと説いている。そして、年齢についての調査、投票率などに言及し、昔、若かったケネディ大統領の演説に触れて文章を終えていた。
ところで、私が政治家の年齢について述べようと思った理由は、自分自身の来し方を顧みて、馬力のあった若い頃を想起し、フランスの首相にエールを送りたかったからである。と言いつつも、私と天声人語の記事がほぼ同じ時期に、政治家の若さのこと、しかも、フランス、アメリカと引合いまで偶然に同じだったことに驚いている。ここで、朝日新聞の人気コラムである天声人語と比べることは、畏れ多いことであるものの、偶然に一致したことに、見えない何かの力が浮かんだ。もしかしたら、事を成す、あるいは事が起きるときには、偶然も重なって、一気にうねりが出来るのかも知れないと、大層なことを思った。
若い政治家について考える人が一人、二人。それが10人、20人と増え、100人、200人とさらに増えて、もっとその先に、さらにさらに増えていくことを想像する。そのようなうねりがあるときに、人知の及ぶところではない偶然が大きな力を呼び出す役割を担うのかも知れない。そして、海の向こうのフランスに限らず、身近でも若者の台頭が用意されるのではないかという夢想に浸るに至った寒中のひと時であった。
反復すること
2023年10月22日
目下併読している本の中に、同じようなことが書かれていた。すなわち、四方田犬彦著『いまだ人生を語らず』に、「本を読むことの本当の面白さは、それをいくたびも繰り返し読むところにある」とある。もう一冊、『日本の最終講義』の中にある木田元の講義録に、「…という本は、ずいぶん何回も読んできました。大学院の演習で何年かかけて読んだこともあります」というように、双方反復して読むことに触れている。
これらの言説に複雑な思いに駆られる。というのは、私はこれまで、数冊を除いてほとんど繰り返して読んだことがないからである。木田元は、繰り返すことによって読み方が変わったことを講義の題目にしていて、その効用を説いていた。一方で四方田は、繰り返して読むことで、それまで読んだときにはなかった異なった姿を見せてくれる、と書いている。さらに彼は、多くを読む必要がなく、いくら一万冊読んだとしても、一度しか読まない人は不幸だ、ということまで記している。
さて、ひとは年を重ね成熟する。さらに長らえると老化という新たな経験が待っている。光陰箭(矢)の如く、時節流るるが如し。古希を過ぎてからというもの、ついこのことわざを口ずさんでしまうほど過ぎ行く時が速い。そのようないまでも、まだまだ興味を惹かれることが多くある。つまりは、知識と経験を広めたい意欲があるのである。また、「時間との戦い」という言葉が現実味を帯びつつあることも加わり、あれこれの書物を手にしている。それはまるで、四方田の言う不幸を重ねているが如くの読書なのである。この私の読み方は、四方田に一刀両断にされるだろうことは明らか。すなわち、私の読書に抱く意欲は、どうも違っているように思う。
そんなある日、読んでいる本に、私はいくつもの付箋を挟むことに思いが至った。付箋の先には、鉛筆で線を引いた文章がある。それは、印象深かった個所の導(しるべ)であり、読み捨てるだけでは惜しいと思ってのことで、いつかは血となり肉となる材料を保存するような意味合いなのである。はて、この私の作法は、読み返しはしないものの、四方田の言う「面白さ」を私も体現しているのではないかしら。何ともはや、「不幸」が一転して、繰り返すことの効用を体現しているではないか、少なくとも形の上では。そこで、改めて四方田の述べている例の個所を、付箋を頼りに読み返してみた。そうしたら、彼にはたくさんの書物があり、そのなかには、装丁が気に入って書棚に置きたいという本もあるようだ。さらに、それらを整理し、最後に百冊ほど、繰り返し読んだ書物を手元に残るようにしたい旨が書かれていた。ふーむ、私とは五十歩百歩ではないかと、妙に共感を覚えたのである。
一度しか読まなかった本は、その一度で満足したことがあれば、読んでも興味を抱かなったこともある。それだけではなく、立花隆も言うように、文章がわからない、あるいはつまらない本に時間を費やすのは人生のむだだと思って切り上げることもしばしばである。
反復して読みたくなるのは、自然の発露だと承知する。また、年を重ねるということは、無遠慮になることでもあり、目下ひとが何と言おうと、私なりの読書を続けたい。一度っきりの著者との出会いも反復することも、残された時間を楽しんだらいい、という結論である。
生活と直感
2023年07月10日
近ごろ、生成AIと称するchatGPTを使って、小説、詩などの知的行動を任せたり、問題の解答を変換してもらったりすることが話題になっている。私はこの生活の変化をまだ享受していないと思いつつも、世の中が急速に変わっていることを感じる。そのような日々、いまの時の流れに抗したことを何かの拍子に、次から次へと思い出した。
ある母親のことである。彼女には嫁いだ娘がいて、娘に実家のあることを用命していた。急ぐことでもなかったそのことを都合のいい日に済ませた、まさにその時に、いま済ませたのではないのかと、娘に電話をかけた。どうも、母親はそのような予感がしてかけたらしい。また、ある刑事さんが、会食の最中に手配中の犯人が近くにいるのではないかと、繁華街に出たところ、果たして見つけて逮捕したということを、ある人のエッセーで読んだ。これを刑事の勘というのだろう。私にもやや似たようなことがあった。私は2019年の秋に、カミュの『ペスト』を読んだ。翌年、コロナ禍に突入したことは周知の事実である。ニュースによると、これを機に『ペスト』が良く読まれるようになったようだが、偶然ではあるものの、先取りして読んだのであった。
このように、小説より奇なりの事実は、探せばある。これら、予感、刑事の勘、偶然の一致という事象、辞書を引くと、各々、虫の知らせ、第六感、原因がわからないことなどと書かれている。総じて、物ごとの真相を心で感じ、直感が働いたと言われる部類のことなのだろうと思う。この直感とchatGPTを大まかに対立する概念として考えてみた。
さて、chatGPTについては、触れたいと思う一方で畏れもあり、何とも気になる存在である。かつて、文明の波が固有の文化のなごりをたいてい流してしまった、と明治維新以降のことを書いたのは寺田寅彦。このように歴史をひも解くまでもなく、chatGPTには変革の大きさを感じ、これまで寄って立った生活の利便がかき回されてしまうのではないかと畏れる。それは、老年期に身を置き、加齢のせいで自らが変革に対応しにくいからだということ、そして、やはりchatGPTに巨大な存在感を抱くからかも知れない。
一方で直感は、我流の解釈であるが、人間の動物たる存在の証であると思うのである。たとえば、鳥は雲行きが怪しくなるなど、天候の変化を察知して低く飛ぶ、というようなことに、私は動物特有の鋭さを感じ、これは直感の部類に入ると思っている。直感は、どの生き物でも生存本能につながっていると愚考する。chatGPTは、直感をもこなして、人間により近づくのだろうか。もしそうなら、それはそれで楽しみなことであるものの、直感を働かせる人間が、人間たる所以を根こそぎに剥がされてしまうのではないかという危惧を抱く。そういえば、件の寺田寅彦は、感覚(五感)の意義効用を忘れるのは、かえって自然を蔑視したものとも言われる、と記している。chatGPT始め、あらゆる機器は、生き物である人間に即応するよう、コツコツと文明に浸透していって欲しいと願う。同時に、機器に溺れないようにすることが、寺田寅彦から学ぶことだと思う。
改めて、生活の中にふと湧き起こる直感を大事にしたいと思う。そして、取りも直さず、文明の「端境期」に直感を損なうことなく毎日を送りたい。ある知人が言うように、直感は裏切らないからである。
時間短縮と相撲立ち合い
2023年04月26日
アメリカ大リーグで「ピッチクロック」が導入され、オープン戦試合時間が短縮されたという記事があった。昨年に比べて、平均すると26分も短縮されたらしい。ピッチクロックとは、投球間隔の時間を制限することであり、ピッチャーは、ボールを手にしてから走者がいない場合は15秒以内に投げる必要があるようだ。
野球は、攻撃と守備を交互に行なう競技である。攻撃側は、打者が一人で向かい、他の人は、ダッグアウトで控えることになっていて、その間は、身体を思いきり使わなくて済む。そのことが、ほぼ全員が走るサッカーなどに比べてスピード感で引けを取ると、私は思っていた。しかし、私の思っていることとは別に、長い試合時間を何とかしようという主催者の思いがあるのだろう。2時間、あるいは3時間くらいかかる野球の試合を、いまの時代にゆっくりと観戦する人が減っているのかも知れない。
さて、時間短縮と言えば、相撲の立ち合いに思いが至る。対戦する力士が仕切りを繰り返し、制限時間になって立ち合うとき、お互いに呼吸を合わせる、その合わせ方が力士によって異なっている。早くに呼吸を整えた力士がいる一方で、ある力士は、後ろにある徳俵まで下がって、なかなか腰を落とすことがない。また、別の力士は、足裏で土俵をこすり、腰をそらし、と相手にお構いなく、自分の呼吸を形作る。両者は相対しているのに、まるで取り組む極まで「別行動」で立ち合うのである。それだけではなく、その動作に時間がかかって、見ているこちらの緊張が切れてしまう。この間を仕切る行司の人たちの苦労が絶えないのではないかと想像する。最近時々十両の相撲も観戦するのだが、ここでも中入りと同じように、別々の動作でもって呼吸を合わせていた。事程左様に、それぞれの立ち合いの動作が異なると、さすがに興趣が減ってしまう。
立ち合いについて調べてみた。戦前の双葉山時代には、制限時間いっぱいになって塩をまいて、相対すると直ちに立ち合っていた。大鵬、柏戸の時代も、千代の富士の時代でも、相対して間を置かずに立ち合っていた。いまとは明らかに違う立ち合い風情なのである。ひと言でいうと、取り組みにスピード感があるのだ。それなのに、いまそれぞれが自分流の呼吸の整え方をするようになったのには、理由があるのかも知れない。少し大雑把ではあるものの、時代順にみてみた。大鵬、柏戸などは仕切り線に手をついてはいなかった。まるで立ったまま立ち合うような格好であった。しかし、千代の富士の時代になると、双葉山時代のように、しっかりと手をついている。ちょうどその頃のある時期に、手をつく、つかないと論争があり、親方衆から指導を受けていたことがあったと記憶している。つまり、千代の富士時代からこちら、手をついたり、つかなかったりと、立ち合いが乱れた。その結果、指導され是正しようとする力士が、手をつくまでに、それぞれのルーチンワークを持つに至ったのではないかと推理してみたのである。
その推理はともかくとして、「別行動」での立ち合いは、見ていて興趣が減るだけではなく、いわゆる相撲取組の型にそぐわないと思うのである。日本相撲協会のHPをみると、「相撲には歴史、文化、神事、競技など様々な側面があり、それぞれ奥深い要素を持っています。」と書かれている。神事であればこその基本動作、文化の側面を担う仕切り、これらをいまの立ち合いから感じ取ることは出来ない。ピッチクロックならぬ「立ち合いクロック」までは求めないにしても、制限時間いっぱいになってからの相撲が醸し出す奥深さを願う昨今である。
誰ぞ常ならむ
2023年03月12日
このところ、光陰、幾星霜、の文字が頭をかすめることが多くなった。いつまでも若くはないことは承知しているつもりでも、いざ年を重ねてみると、これまでの歩みの早さと、寄る年波には勝てないことに、はっと気がつくこの頃である。先だって、大学でワンダーフォーゲル部活動を共にした先輩、同輩と宴の機会をもった。昨年9月、やはり部活を共にした先輩を亡くしたことから、お互い会えるうちに会っておこうと企画したのが年の始めだった。
先輩とは、何10年ぶりかの再会で、頭髪も含めて変わらぬ姿に驚いた。昔、彼の結婚式に招かれたときには、当時私が吹いていたフルートを披露、また、私の結婚式では司会をお願いした仲であった。同輩は、卒業後に部活をさらに発展させて、登山家の植村直己の探検に、医療班としてエベレストなどへ同行した猛者であった。彼とも10数年ぶりの顔合わせで、約束の食事時間より2時間早く待ち合わせて、喫茶店で時間をつぶした。
ご多分に漏れず、久々の再開は昔話から始まった。そして、話は最近の各々自身の身体の具合に及び、それは、3人になっても同じ話が続いたのであった。一般に、先輩とはありがたいものである。学生当時、この先輩が授業で取ったノートは有名で、私は、○○ノートと彼の名前を冠して、よく借りたことを当日別れてから思い出した。医師は、症状を聴き、診断して治療するという手順を踏むことを生業とすることは言うまでもない。その「当たり前」を彼が取ったノートにびっしりと書かれていた文字面が示してくれていた。
同輩は、己の優秀さをおくびにも出さない。むしろ、冗談が好きなのだろう、当日も先輩や私に対して、昔に発した言葉をうれしそうに再現、繰り返したのである。その彼が当時の資料を携えていて、見ると確かに優秀だったことの証拠が残されていた。
10代でこの仲間と知り合って、半世紀以上が経った。各々、変わらないようでいて、そこかしこで年数の長さを感じる。それを端的に感じるのが病を得たことなのだろうと思う。私だけではなく、先輩も同輩も少なからず経験してきている。「我が世誰ぞ常ならむ」と詠むいろは歌は、こういうことなのだろうと思いながら帰宅の途に就いた。そして、当日別れてから、同輩がよこしてくれたショートメールに、「思い出を確認するのも良いもんだね」と書かれていた。私は、妙にこの言葉に引っ掛かった。
私は、大学だけではなく、高校や中学の同期会にしばしば出席する。そこでは、昔話と現況に終始する。それはそれでいい時間なのだが、集まる前から、ああ、また同じことになる、と予想できることでもあった。しかし、同輩のメールの文言を読んで、眼が覚めたような気持ちになった。すなわち、思い出を確認する良さは、今だけではなく、すでに短くなった「これから」を見据えることなのだと、改めて思ったのである。それは、彼も先輩も当日発した言葉の端々に、病に屈してはいないと私が感じたことにもつながることである。いろは歌は、「浅き夢見じ酔ひもせず」と結ばれる。歌のように現世を超越することは、難しいものの、古希を超えた私に要る、超然とした心構えを抱かせてくれたひと時であった。
おじさんと私
2022年12月03日
ある都会の小路で信号待ちしていたとき、私のすぐ前を初老の男の人が通り過ぎて行った。細身で、髪はどちらかというと薄く、腰痛持ちなのか、やや前かがみに歩いていた。その人は、特に目立ったわけではなく、無礼な言い方をすると、どこにでもいるおじさんであった。そのおじさんの後ろ姿を見ていたら、遠い昔のことが浮かんできた。
私が子どもだった頃、周りにはおじさんが大勢いた。彼らは大きな声で話し、体格も子どもより大きいから、近寄りがたい人が多かった。そんな中で、子どもを見つけると否応なく耳を引っ張って、恐怖に陥れるおじさんがいた。無論、この人は例外中の例外であったが、中には、優しくて価値観を拡げるに資するおじさんもいた。すなわち、私の周りに、怖さと優しさが綯(な)い交ぜのままに、親とはちがう大人がいることを知ったのである。それは、親に包まれた関係とは異なることであり、畏怖を抱くことにもなったのであった。
時が経ち、私は中学、高校と進み、さらに大学生、社会人となっても、おじさんはいた。そのおじさんは、いつもほとんど子どもの時に抱いた印象のままであった。そして、気がついたら私がおじさんになってしまったのである。それだけではなく、さらに年を重ねるうち、おじさんは年下になってしまったのだ。そのことは、街中で見かけたおじさんの様子から伺えた。また、テレビに登場するおじさんも、画面に名前と年齢が示されていて、はっきりと年下であることがわかる。つまり、私が何歳になっても、おじさんは周りにいるのである。そして、何と年下のおじさんにも畏怖を抱いてしまうのである。何だか、おじさんに対して、頭が上がらないが如くだ。
さて、世の中は、いつも変わらないと思うことがある。テレビに登場するアナウンサーは、何年経っても同じような年恰好のひとがニュースを報じている。私の好きな相撲もそう。私の若いときもいまも主に20代である力士が活躍している。とはいうものの、いつの間にか力士は平成生まれになっている。これを輪廻というのか、私の前に同じような景色を提供しながら時は移り行くのだろうと愚考した。
肝心のおじさんも、私の生涯を通して同じ出で立ちで現れる。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」と書かれているのは、彼の方丈記。私には、「おじさんは絶えずして、しかももとのおじさんにあらず」の心境である。